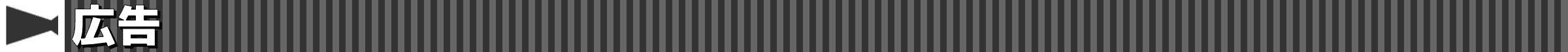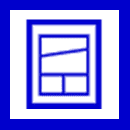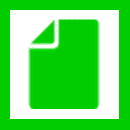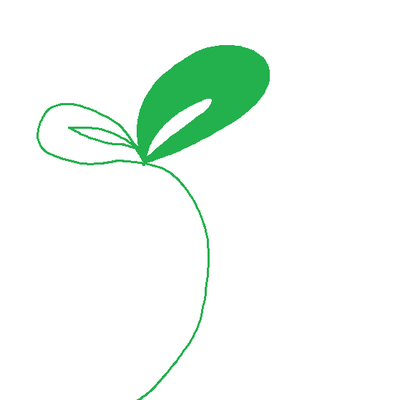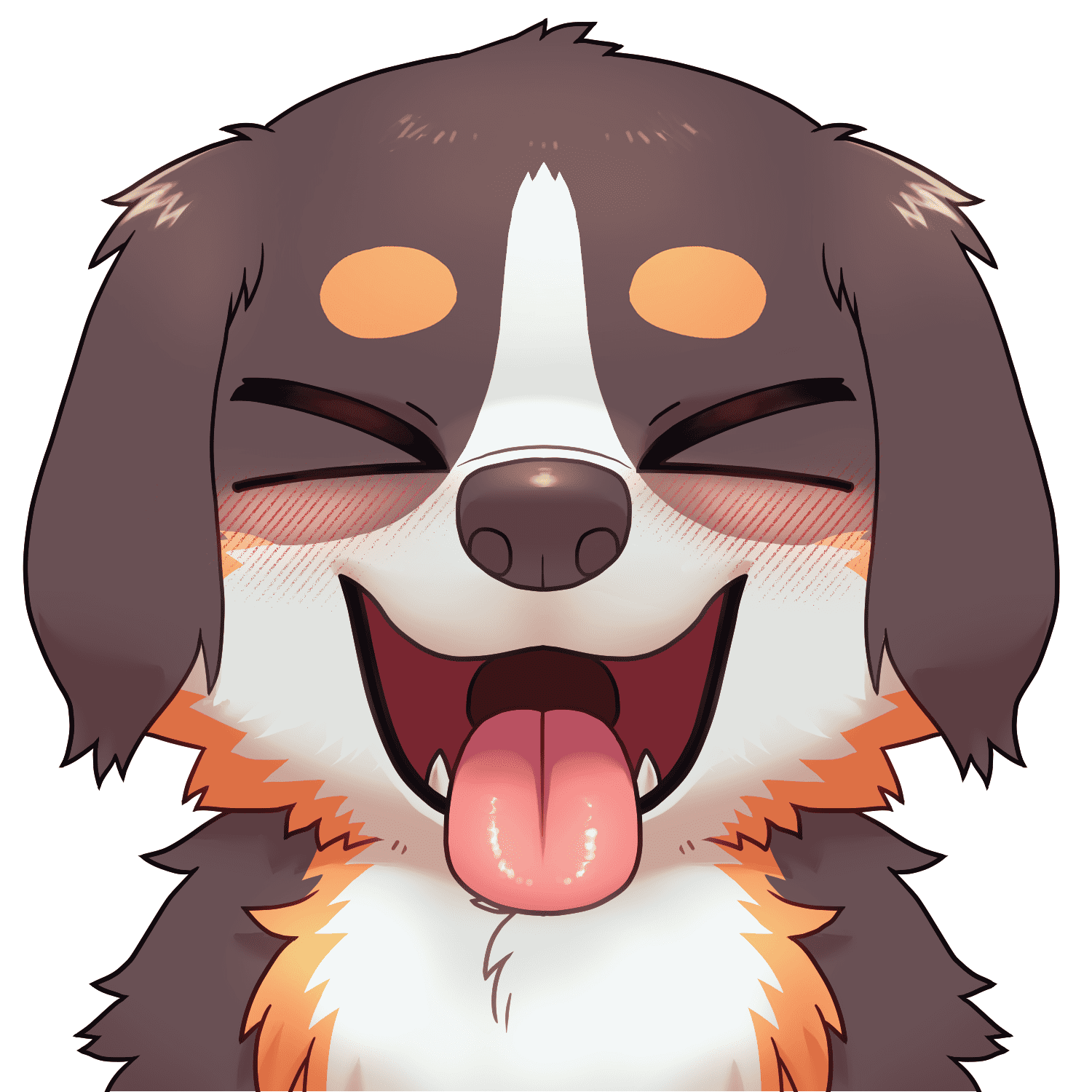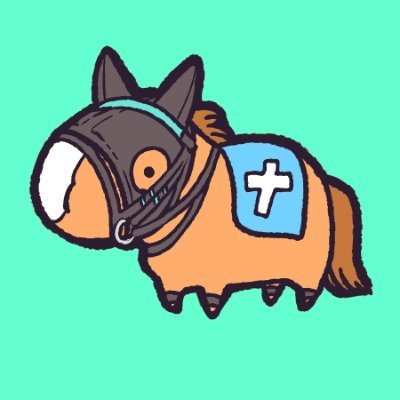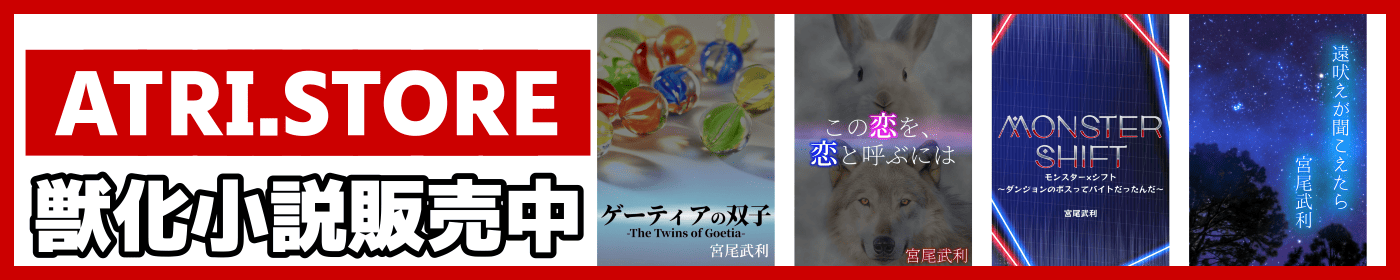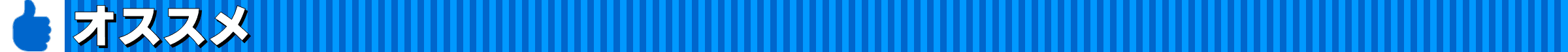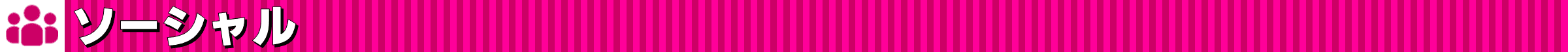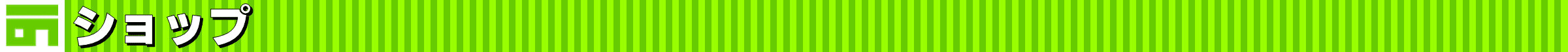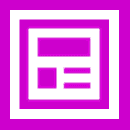
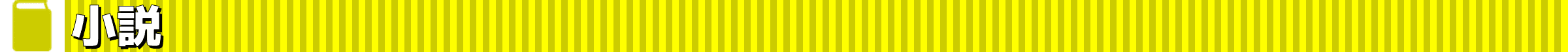
ようこそ異世界カフェへ!
最近様子がおかしい委員長が、とあるビルに消えていくのを目撃した私。偶然そのビルに出来たカフェに誘われた私はクラスメイトと共にその店を訪れることに。その店は異世界カフェ。異世界人が働くはずのこの店で出会ったバイコーンの青年にはどこかの誰かに似た面影を感じて……?
皆少しずつ色々な秘密を抱えていて、でも皆自分の秘密に向き合い始めていて。その中で少女たちは答えを探していく。
最近、委員長の様子がおかしい。
まぁ、以前からちょっと風変わりではあるけど、学級委員長をやってて、勉強も出来て、まじめで、眼鏡ではあるけど、普通に明るいし、誰とでも仲良く会話するタイプで、そこまでお堅くはない人柄ではある。
でも、最近ちょっとよそよそしいというか、なんかちょっとそわそわしてることが多かったり、放課後とっとと一人で帰ったりして、付き合いがちょっと悪くなったような気がする。気がする、だけかもしれないけど。
「どう思う?」
「どうって、委員長?」
休み時間、クラスメイトに問いかけられ、私はちらりと委員長の方を見た。
「最近、ちょっと変じゃない?」
「うーん、どうだろ」
私はあまりそういうのは詮索しない方がいいのかなと思って、言葉を濁したけど、まぁ気にならないといえば、嘘になる。
「最近、先に帰っちゃうし、そわそわしてる気がするし」
どうやら思ってることはみんな同じっぽい。
「彼氏かな?」
まぁ、そういう可能性も考えなくはない。だからこそ、あんまり詮索するのも悪いなーと思いつつ、気になる下世話な気持ちも分からなくはないし。
「バイトかな?」
それも可能性あるかも。うちはバイト禁止じゃないけど、働いてるとこ見られるの普通に恥ずかしいし。
「普通に塾とかじゃない?」
委員長だし、その可能性もゼロじゃないけど、だとしたら別によそよそしくする必要なくない? とは思う。
「何か、よからぬことに巻き込まれてたり?」
いやいや、委員長に限ってそれはないんじゃないのかな。委員長に限って。
「気になっちゃうしさ、つけてみない? 放課後」
「いや、それは流石にやりすぎじゃない?」
気になるのは分かるけど、それぞれ事情があるんだろうし、私たちに言わないってことは、言いたくないんだろうし、それをつけてまで探るっていうのはやりすぎな感じがした。
「うーん、まぁ、そうかなぁ、そうかも」
「別にいいんじゃない、それぞれさ、あるじゃん。別に」
それぞれ言いたくないこと、知られたくないことは別にあるんだし、それをわざわざ知ろうとするのは、野暮だなと思うし、私がもし詮索されたら、それはちょっと嫌だなと思うし。
「まぁ、そうだね、じゃあそっとしておくかー」
クラスメイトもあっさり引き下がってくれて、ほっとした。他人が知られたくないと思っているものを、わざわざ知っちゃうのも、ちょっと気持ちがよくないと思っていたし、大体委員長なら、よからぬことに巻き込まれたりしているとは思えなかったので、特に心配していなかった。
けど。その日の放課後。買い物ついでに町中に寄った時だった。
本当に偶然だった、とあるビルの前で周囲に気を配りながら、そそくさとそのビルに入っていった委員長の姿を見てしまったのは。
……多分、見てはいけないものを見てしまったような気がする。
私は、少し時間を置いてから、委員長の入っていったビルの前に立って、ビルの看板や、中を見る。まぁ別に、怪しい雑居ビルというわけではない。学生も出入りするような、複数の本屋さんとか服屋さんとか、喫茶店が入っている普通のビルだ。ただ、本屋といっても普通の本屋というよりかは漫画寄りの、服屋もコスプレ中心の、喫茶店もコンセプトのあるカフェで、言ってしまえばサブカル寄りのお店ばかりが複数入っている、そういうタイプのビルではあった。
そのビルの中に、委員長が消えていった。ということは、どういうことだろうか。
普通に本を買いに来たのなら、別にあんなにこそこそする必要はないはずで。わざわざこそこそしているのは、多分知られたくないことだからで。
……うん。多分、見てはいけないものを見てしまったんだ。確実に。
これは黙っておいた方がいいな、詮索しない方がいいなと思い、その日はそのビルを後にした。
けど、次の日。例によってクラスメイトから話しかけられる。
「ねぇねぇ、最近話題のこれ、知ってる?」
手渡されたのは、とあるチラシ。とあるコンセプトのカフェのチラシだ。そのカフェの住所は、昨日委員長が入っていったあのビルだった。
「……異世界カフェ?」
「そ、ワイドショーとかでも取り上げられてて」
「へぇー」
私はちらりと委員長の方を見る。こちらを気にする素振りは見えない。こっちの会話は聞こえていないようだ。
「ほら、最近異世界人とかちらほら見かけるようになったじゃん? 交流も増えてきてさ。こういうお店も増えてきて」
あのビルにコンセプトのあるカフェは複数入ってるし、本屋もあるから、委員長がこのお店に入っていったかは分からない。でも、話題のお店であれば、委員長が足を運んでいてもおかしくはない。
「折角だしさ、みんなで行かないかなって? どうする?」
「行く。面白そうだし」
昨日は反対した私も、今日は即賛成した。委員長がもし本当にそこに足を運んでるんだったら面白そうだなという興味もあってのことではあるけど、それ以上にそのカフェ自体にも強い興味があった。異世界のこと、実は以前から結構気になってはいたからだ。
「委員長にも聞いてみる?」
「あ、そうだね」
クラスメイトは、委員長にも声を掛けてみる。
「委員長さ、これ興味ある? みんなで行こうかなって」
「え……えっ! あっ……あの……いや、私はいいかな……」
「えー委員長こういうの好きそうじゃん?」
「好き! あ、好きでは、あるんだけど、その……今日はやめておこう、かな……うん……」
分かりやす。え、分かりやす。めっちゃ分かりやすいリアクションするじゃん。委員長、絶対このカフェのこと知ってるじゃん。
「そっかー。じゃあまた今度誘うね」
「あ、うん。いや……うん」
嬉しそうな、寂しそうな声を上げて、委員長は俯いた。絶対本当は来たかったけど、行けない人の反応じゃん。分かりやす。
「委員長、やめとくって」
「うん、聞こえてた、また今度に誘おうよ」
委員長の反応が妙だったことはクラスメイトも気づいてたと思うけど、それがどういう意味の反応かは、分からなかったと思う。私だから、昨日ビルに入っていく姿を見ていたから、その意味を何となく察しただけだ。でも、そこまで分かりやすい反応をする理由はよく分からないし、だからこそなおのこと、そのカフェのことが気になってきた。
その日の放課後、私たちは他の何人かの友人たちとそのカフェへと向かった。昨日委員長が入っていったビルの某階。そこそこ混んでて、30分ほど待った後に店内へと通される。
「ようこそ異世界カフェへ!」
出迎えてくれたのは、悪魔、幻獣、ドワーフなど、様々な種族の人たちだった。
店内は、ビルの他のテナントとは雰囲気がまるで違う、異世界情緒あふれる作りになっていた。
私達の世界が異世界との交流を始めたのは、今から100年以上前。でも、なかなか双方の交流が円滑に進むのに時間がかかったけど、ここ十数年で一気に進んで、徐々に異世界人も珍しくなくなってきた。
でも、文化に触れる機会、知る機会はまだまだ多くなくて、そこにビジネスチャンスを見つけたのか、こういうお店が徐々に増えてきてるらしい。
異世界、と一口に言っても、勿論複数の世界があるわけで、こういう一括りのお店は複数の異世界がごっちゃになってるから、文化を知るという意味では、正しい理解を出来るわけではないけど、それでも触れる機会を作る意味はあるとは思う。私も、実際文化のことをもっと知りたかったし。
「では、ゆっくり楽しんでいってくださいね~」
エルフ族、という言い方が合っているのか分からないけど、すらりとした耳の長い美人のお姉さんに案内されて、私たちは席に着く。複数階をぶち抜いた店内はかなり広く、各席から中央の舞台がよく見えるように円形に配置されており、つくりはカフェというよりもはやホールに近かった。多分、景気が良かったころに作られたものをぶち抜きこのカフェは複数の異世界を合わせたコンセプトらしく、軽食も飲み物も複数の世界それぞれの文化を意識したものになっている。
「じゃあ私これにしようかな」
「なら私こっち」
クラスメイト達が次々選んでいく中、私はじっとメニューを見ながら悩んだ後、顔を上げて店員を探す。そして、通りすがった一人の店員が目に留まる。すらりと背が高く、突き出した凛々しい鼻と銀色の美しいたてがみを持ち、二本の角を生やした黒毛の馬頭を持つ、バイコーンの青年だった。多分現地の衣装である、この世界のタキシードに似た服をびしっと着こなしたその店員に、私は声を掛ける。
「すみません、いいですか?」
「えっ……あっ! ……んっ、あ、あぁ、私ですね、失礼しました。どうぞお申し付けください」
バイコーンの青年は、一瞬高い声色で戸惑った後、低くかっこいい声で、凛々しい表情で私に返事をした。逞しい体とは裏腹な優しそうな目元に、それこそ目が奪われたけど、さらによく見ればその瞳孔は横に長く、本当に私たちの世界の人間とは違うんだなと感じさせられた。けど。全く違うはずのその目元には、何だか不思議な親近感も感じていた。
「……あの、このオムライスなんですけど、このアレンジ元ってお兄さんの世界の料理ですよね。どういう料理ですか?」
「あぁ、それはですね……」
バイコーンの青年は、私の質問に丁寧に答えてくれた。分かりやすい説明はまるで、勉強が苦手な生徒に教えるかのようだった。
「ありがとうございます、このまま注文しても大丈夫ですか?」
「ええ、どうぞ。皆様も合わせてお伺いしますね」
バイコーンの青年は注文を全て聞いた後、深々とお辞儀をして席を離れた。
「あんたってさー、結構こういう時グングン行くタイプなんだねー」
「うん、まぁ気になったことは聞いた方が早いからね」
私の様子を見たクラスメイトにそう言われたけど、色々気になっていたことはあるから、それも含めて聞いてみたかったのもあったし。
「あのバイコーン、ちょっと気になってたし」
「ああいうのがタイプ?」
「……まぁ、強い否定はしないけど、ってくらいかな」
「なるほどねー。でも実際イケメンだよねー。バイコーンって言うんだー」
クラスメイトと会話をしながらも、私はちらちらとバイコーンの姿を目で追っていた。
料理を運んでくれたり、他のお客さんと接客してたり、色々な姿をじっと見つめていた。そしてそんな私の視線に気づくと、バイコーンはそっと目線を逸らした。
みんなそれぞれ料理を食べたり、雰囲気を楽しんだ後、各異世界の文化を基にしたショーを堪能した。
そんなショーの一つに、私は特にくぎ付けになった。
さっきのバイコーンをはじめとした幻獣族の人物たちが出てきたショーだった。
さっきまでの黒い衣装とは打って変わって、派手なローブの様な衣装に着替え、次々舞踏や演武を披露するその姿に、私は心を奪われた。この世界の獣に似た姿の姿をした、屈強な人たちの力強い姿のかっこよさ。そして一番の見どころはショーの終盤だった。グリフォン、ドラゴン、フェニックス。幻獣族の人たちが、次々と元の獣の姿に変身し、様々なパフォーマンスを披露していていく。勿論あのバイコーンも力強い馬へと変身し、舞台を跳ね回っていた。その力強い姿が私の目に強く焼き付き、ますますあのバイコーンのことが気になった。
ショーを終えて、再び獣人の姿に戻り、黒い衣装を着直したバイコーンの青年は、私たちを見送ってくれたけど、私がじっと見つめているとやっぱり目線を逸らした。
私達は、興奮冷めないままお店やショーの話をしながらその日は帰路に着いた。だけど多分、私は他のクラスメイトとは少しだけ違う興奮を胸にしまって、その日の夜を静かに胸を高鳴らせたまま過ごした。
その次の日。休みの時間、学校の裏に、私は委員長を呼び出した。
「二宮(にのみや)さんってさ、バイコーンだよね?」
単刀直入に、私は切り出す。委員長――二宮さんは、一瞬固まった後、周囲を見渡して他に人がいないかを確認し、私につかつかと歩み寄った後、顔を近づけて、耳元でささやく。
「他の人に言ってない?」
二宮さんが顔を離したのを見て、私は小さく頷いた。
「……放課後、改めて話をしましょう」
二宮さんは小声でそう言って小さく頷き、私を残して早歩きで教室へと戻っていった。
そして放課後、町中のカラオケボックスで私たちは向き合っていた。
「二宮さんさ、バイコーンだよね?」
私はもう一度、同じ質問をする。二宮さんはまた少し固まった後、ドリンクを口に含み、深く息を吐き出した。
「いつ、気づきました?」
「ごめん、一昨日かな? たまたまビルに入ってくところを見ちゃって……」
「あぁ……」
「で、昨日誘った時不自然な断り方してるの見て……」
「あぁ……」
「で、バイコーンに話しかけた時、一瞬聞こえた声がそっくりで……」
「あぁ……」
「で、そこからずっと目線合わせてくれなくて……」
「あぁ……」
二宮さんはもう一度ドリンクを口に含んで、深く息を吐き出した。
「私、そんなにバレバレ?」
「バレバレ」
「そんなに?」
「そんなに」
二宮さんは天を仰いだ。自分がそういうところをごまかしきれなかったのが、割とショックだったらしい。
「でも、他の人に言ってないんだよね?」
「言ってない」
「ってことはバレてないんだよね?」
「多分。ビルに入る姿を見たの私だけだし、他のみんなは、なんか挙動不審だなーくらいにしか思ってないんじゃないのかな?」
「なら、いっか。いやよくないけど。でも、一旦いいや」
二宮さんは深くため息を黙り込んでしまった。私はドリンクを口に含み、少し間を空けて二宮さんに問いかける。
「言いたくないなら言わなくていいんだけどさ。何で隠してたの? 別にうちバイトOKだよね?」
「いやなんかクラスメイトにああいう姿は見られたくないっていうか……」
「あぁ……」
「こうして説明しなきゃいけなくなるの、面倒っていうか……」
「あぁ……」
「……自分の出自のこととか、色々想像で言われたくなかったから……」
二宮さんはそう言って、やや俯いた。あのバイコーンが二宮さんということは、つまりは二宮さんはバイコーンということ。当たり前のことかもしれないけど、それは大事な意味を持っている。
二宮さんはこの世界の人間ではなく、異世界の人間、幻獣族ということだ。
異世界との交流が始まったのは100年以上前。交流が盛んになったのが十数年前。でもその間に移住は進んでいたし、異種族間の婚姻の例も少なからずあった。その中で、この世界の人間と異世界の人間の双方の血を引く子は少なからず生まれていったわけで。
「バイコーンの血を引いてるってことだよね」
「別にバイコーンの血のことを隠そうと思って隠してるわけじゃなかったし、偏見があるとは思ってないんだけど……そのことで注目を浴びるとかあったら、ちょっと面倒だなって……でも、バイコーンとしての自分を活かせる場がどこかにないかなって思って」
「それで、あそこで働いてたんだ」
「うん。あそこのお店は幻獣世界出身の人多いし。元々、うまく変身出来なかった私に、色々手ほどきしてくれたのもお店の人で」
「親は?」
「バイコーンのはお父さん側の血なんだけど、お父さんもあんまり変身得意じゃなくって。でも私、自分の中のバイコーンをただずっと抱え続けるのも、私はちょっと違うかなって思って。だからこの仕事をしようって思って」
「……そっか。ありがとう、ごめんね。話しづらそうなことを、色々聞いちゃって」
二宮さんは首を横に振った。そして少し俯いて黙り込んだ後、私の顔色を窺うように、ゆっくりと顔を上げる。
「私の方も、聞いてもいい?」
「いいよ」
「……その話を、わざわざ聞いてきたってことはさ。聞きたいこと、それだけじゃないってことでしょ? 一城(いちじょう)さん」
私の名前をしっかり呼びながら、私をじっと見つめながら、二宮さんは問いかける。
「私の出自を聞いて、はいそれで終わりです。ってわけじゃないんでしょ? 他にもっと聞きたいことがあるから、知りたいことがあるから、私に話しかけてきたんでしょ?」
「どうしてそう思う?」
「別に、気づいてたよ。お店でずっと私のこと、バイコーンのこと見てたの。それにそもそも、幻獣族じゃなきゃ普通は知らない料理のことを、わざわざ幻獣族の私に聞いてきたことも。幻獣族について知っていて、でももっと知りたくて。だから、私を呼び止めたんでしょ?」
二宮さんの言ってることは、ほぼその通りだ。異世界のこと、幻獣族のこと、私はもっと知りたい。
それはそうだ。私はもっと、自分のことが知りたい。
「うん、だから二宮さんがバイコーンだって気づいて、バレバレだったよって言うのすごい申し訳なかったんだけど。でも、今の私にとって、相談出来る相手って、二宮さんだけだと思ったから。多分、私達って同じような境遇だから」
私はじっと二宮さんのことを見つめる。
「私は、もっと知りたい。自分のことを……幻獣族のことを、ユニコーンのことを」
私の目を見て、二宮さんは少し嬉しそうな、少し嫌そうな、丁度絶妙な表情を見せた。そして。
「……今日、お店定休日なんだけど。練習で空いてはいると思うからさ、来てよ折角だし。私、一城さんともっと、ちゃんと話したい」
二宮さんの言葉に、私はゆっくりと、大きく頷いた。
そして私たちはカラオケボックスを出て、三日連続であのビルへとやってきた。
「あれ、アンちゃん。今日予定入ってたっけ?」
お店の人が、二宮さんの名前を呼んで問いかけた。二宮さんは小さく会釈して答える。
「お疲れ様です。いや、入れてなかったんですけど、ちょっと急に使いたくなって。その……」
二宮さんはどう説明しようかと悩みながら、連れてきた私の方を見た。お店の人は、私を見てはっとした表情を浮かべる。
「あぁ、昨日の来てた子……制服で分かったけど、アンちゃんの」
「クラスメイトの、一城コウです」
「一条さんね。あー、言われてみれば、そうかもね。奥の三番空いてるから、使って大丈夫だと思うよ。二時間後にはステージも一瞬空くと思う」
「ありがとうございます。後で入れときます」
二宮さんは、お辞儀をして奥へと歩いていく。私も同じようにお辞儀をして付いていった。
「今の、昨日のエルフのお姉さん?」
「うん、いい先輩だよ。色々教えてくれて」
二宮さんは奥の三番の控室のドアを開けて、長机の上にかばんを置いたので、私もその隣にかばんを置いた。
控室は少し広めの会議室という感じだけど、ロッカーがいくつも並んでいて、ドレッサーの他にも壁一面が鏡になっていた。
「待っててね、今ここの会議室、アプリで押さえるから」
「そういうのも今はアプリなんだ」
二宮さんがスマホをちょこちょこ操作すること数分。
「よし、取れた。じゃあ改めて。ちゃんと自己紹介しようよ。お互いの本当の自己紹介をさ」
二宮さんが私の方を向いて、眼鏡をとる。
「私は、二宮アン。バイコーンの、二宮アン」
「……一城コウ。ユニコーンの、一城コウ」
そう、私はユニコーンだ。といっても、それが本当なのか私もよく分かっていない。私も二宮さんと同じでユニコーンの血を引いているけど、変身出来ずに育ってきた。それでもいいかと今までは思ってきた。でも昨日、二宮さんの、バイコーンの姿を見て、自分の中にずっと秘めていたユニコーンの気持ちが、心が、抑えきれなくなっていたことに気が付いた。
「一条さんって、幻獣族のことどれくらい知ってるの?」
「あまり知らない、って言っていいかもしれない。幻獣文字とかは多少は読めるし、どういう種族かとかは何となく分かるけど、知識の範囲ってくらいで。体のこととかは」
「ユニコーンのこと、知りたいっていうけど、どこまで? 私も別に、詳しくないよ?」
「……知識というよりは、体のこと、これからのこと。自分にユニコーンの血が本当に流れているなら、ユニコーンとして生きるなら、どうしていけばいいのか。全て知れなくても、考えるきっかけにはしたい」
「……分かった。じゃあ、今日はまずさ。ユニコーンになってみようよ実際」
「なれる、かな。私」
「それはわかんないけど。やってみようよ。私も、自分以外の人が初めて変身するところって見たことないし。私も、自分のことは知りたいし。ユニコーンとバイコーンがこうして出会えたのもさ。ただの偶然じゃないと思うし」
そう語る二宮さんは、どこか嬉しそうだった。種族的に近縁ということもあって、親近感も湧いたのかもしれない。かくいう私もそうだった。
「二宮さんって、自分で変身をコントロール出来るの?」
「今はね。最初ちょっと苦労したけど、今は大丈夫。でも一条さんは私もいるし、多分難しくないかも」
「二宮さんがいるから難しくないっていうのは?」
「意識のし方とか、体の使い方とかかな。近い種がいないとなかなかいいアドバイス聞けないし」
二宮さんはそう言って、ロッカーから衣装を二着取り出した。昨日バイコーンが着ていた衣装の、黒い方だ。
「これ、二宮さんの?」
「背格好近いし、多分着れると思うよ。あ、クリーニング出したやつだから安心してね」
少し照れ臭そうにそう笑った。
「ショーで着てる派手な方と違って、こっちの黒い方は見た目かっこよく見えるように結構ぴっちりしてるから、ちょっときついかもしれないけど。ある程度動きやすいようには作ってあるけどね。体のライン出て、より変身した感じが出ると思うから」
二宮さんは、手際よく制服を脱いで、衣装に着替えていく。
「……よし、じゃあとりあえず、私変身してみるね。見てれば、感覚とか分かると思うから」
二宮さんは一つ息をついて、背筋を伸ばし、ゆっくり肩の力を抜く。
「まず、今の自分の姿を意識する。そして自分の内側にいるバイコーンの姿を意識する。両方を、形を、しっかり、意識する」
二宮さんは体を軽く振るわせて、指先をゆらりと振るわせる。空気が、ピリッと張り詰めるのが分かった。そして次の瞬間。
「っ!」
ピキッ、二宮さんの指が軽く音を立てたかと思うと、一気にぶわっと黒い毛が噴き出し始めた。二宮さんの柔らかな肌が、腕が、脚が、黒い毛でどんどん覆われていく。
「自分の、姿と……バイコーンが、入れ替わるのを……置き換えるのを、意識すれば……体が、変わってくから……!」
説明している間にも、二宮さんの体は徐々に変わっていく。五本の指が生えていた足は、蹄へと姿を変えていく。お尻には銀色の、ふさふさの尻尾が生えていた。体は一回り、いや二回りほど大きくたくましくなり、そして首筋は太く長くなり、やはり黒い毛が覆っていく。その形はあっという間に、人間の女の子からかけ離れていく。
「ふぅ、フゥ……!」
荒れる呼吸と共に、二宮さんの変化はとうとう顔へと及んでいく。鼻先が前へと突き出し、耳は頭の上で長く伸びていく。目の瞳孔は横に長くなり、しなやかな黒髪は、煌びやかな銀のたてがみへと姿を変えていく。そして頭の上からは、二本の鋭い角が姿を現した。全ての変化を終え、そこにいたのはもう二宮アンという少女ではなかった。その面影をほぼ残さない、一人の逞しいバイコーンがそこに佇んでいた。微かに優し気な目元に、辛うじて面影を感じるかどうかというくらいだった。
すごい。これが、幻獣族の変身。本当の姿になるということ。私は息を止めてただただじっとその変化を見つめていただけだった。
「フゥ……こんな感じ、かな……」
逞しい体躯で二本足で立つバイコーンは、しかしその筋骨隆々の見た目とは裏腹の、二宮さんそのままのかわいらしい声で私に語り掛けてきた。
「どう、かな。これが、私の本当の姿。バイコーンの本当の姿」
「かっこいい、本当に。本当に」
「ふふ、ありがとう」
黒馬は静かにはにかんだ。
「まぁ、本当の、と言っても、本当の姿のうちの片方でしかないけど……でも、この姿も私は好き。勿論、人間の姿も好きだけど。こっちの自分の方が、自分だって感じがするんだよね。私の場合。一条さんは、どう思うか。やってみて」
私は小さく頷き、手渡された衣装に着替えていく。さっき二宮さんの着替えを見ていたから何となく段取りは分かるけど、不安な部分は二宮さん――バイコーンに聞きながら進めていく。でも、元々私とほとんど背格好に差のなかった二宮さんが、バイコーンとなった今私よりもずっと目線も高くて肩幅も広くて、何だか不思議な感じがした。
そうして黒い衣装を着てみたけど、人間の姿ではぶかぶかだった。今から、これに合う体に、私もなれるだろうか。
「私の変身を意識しながら、自分の中のユニコーンに問いかけるように、引き出すように」
二宮さんの言葉を聞きながら、二宮さんの変身を思い出しながら、自分が変身する様子を思い浮かべる。
まず、私の中にいる本当の自分、ユニコーンとしての私ってどんな姿だろう、まずはそこから思い浮かべる、というよりは、思い出すの方が近いかもしれない。自分のユニコーン姿は当然見たことないけど、でも勝手な想像として存在するわけじゃなく、確実に私の中に、確かなユニコーンがいるはずで。そのユニコーンの姿を自分の中から引きずり出さなきゃいけない。
肩の力を抜く。足を肩幅に広げる。体をぶらりとさせた後、自分の腕を前に上げる。この手が、この足が、この体が、この顔が。今から、変わっていく。それは、どんな姿か。
「しっかり形を意識して。自分の今の姿を。その下にある、ユニコーンの姿を」
人間を着ている今の私。その内側にいる、ユニコーンの私。その表裏を、これから入れ替える。すっかり、完全に入れ替えていく。うっすらと目を開けて、自分の手を見る。それはすらりと長い五本の指の、人間の手だ。だけど同時に、まるで重なるように、太い指で、白い毛で覆われた手も見えた。そう、白い毛だ。私の、ユニコーンの体に生えているべき毛だ。
足に意識を集中する。
お尻に意識を集中する。
そして、顔に意識を集中する。
……うん、大丈夫だ。イメージ出来た。私の中のユニコーンの、蹄が、尻尾が、馬の顔が。私の内側から飛び出すのを待っているのを、しっかりイメージ出来た。大丈夫。私は、知れる。私自身を。きちんと向き合える。
「イメージ出来たら、入れ替わるのを、置き換わるのを想像して!」
言われた通り、私はイメージする。ユニコーンの自分が、表に出て行く様を。本当の自分が、姿を現すさまを。そして。
ピキッ。
微かに手の指から聞こえた音。二宮さんがバイコーンになる時にも聞こえた、あの音だ。体が変わっていく、歪んでいく、確かな音だ。
「ぁ、うぁ……!」
経験したことのない感覚が、指に、腕に、背中に走る。痺れに似てはいるけど、全然違うかもしれない。あえて言うなら、「はがれる」感覚。私が、私を脱ぐ感覚だ。その感覚と共に、私の体は劇的に変化を遂げていく。
目の前に伸ばした手の甲に、びっしりと短い白い毛が生え揃っていく。まるで太い筆で塗りつぶしていくかのように、瞬く間に私の手が、腕が、毛で覆われていく。衣装で隠れて見えないけど、毛が生えていく感覚はそのまま背中にも、腰にも、腹にもわたっていく。それと共に、自分の体が大きくなっていくのも実感していた。
急な変化に少しよろめいて、半歩後ろに下がった時だった。ふと地面に付いた足が、こつんと音を立てた。聞き慣れない音だった。すぐに私はその音を理解する。足が、蹄に変わったんだ。もう、私の足は人間の足じゃないんだ。ちらりと見えた脚ももう、白い毛で覆われていた。
「ぁっ……!」
そう言っている間に、お尻のあたりからぶわっと何かが噴き出すのを感じた。見ればそこには、黄金色のキラキラした尻尾が生えていた。人間には本来生えていない器官が自分の意志で動かせるのは、すごく不思議な感じがした。そして、私の体の変化は体にとどまらない。
「う……ウゥ……!」
体が大きくなり、ぶかぶかだった服もだいぶフィットしてきた。首回りも余裕があったはずなのに、すっかり合うくらいまで太くなっていた。そして、目線がどんどん高くなっていく。首が伸びているんだ。そして、変化はついに顔に到達する。
私の黒い髪の毛が、黄金色のたてがみへと色づいていく。白い毛は顔をも覆いつくし、それに合わせるかのように私の顔は鼻先が突き出し、前へと飛びていく。人の顔から、馬の顔へ。一城コウという人間の部分が、ユニコーンという幻獣に、置き換わっていく。耳も頭の上でピンと立ち、最後に額から長く鋭い角がピキピキと伸びていく。その角がすっかり生え切った瞬間、それが一城コウが消え、ユニコーンが完全に表に出た瞬間だった。
「ハァ……ハァ……私、どうかな……なれてる……?」
「うん、そうだね……折角だから、鏡で自分の姿を見て見なよ」
バイコーンに促されて私は鏡の前に立つ。果たして、鏡の向こうに立っていたのは、黒い衣装を身にまとい、二本足で立ち、頭に大きな一本の角を持った、白い馬だった。まさしくその姿はユニコーンだった。
私が動けばユニコーンも動く。たてがみが、尻尾が、緩やかになびく。このたてがみも、この尻尾も、私のものなんだ。
このユニコーンが、私の姿なんだ。
「二宮さん、私っ」
「うん、立派なユニコーンだと思うよ。かっこいい」
ふとバイコーンと向き合うと、さっきまで大きく感じていたバイコーンと目線がほぼ同じ高さになっていた。でも、よくよく見ると、バイコーンよりかは少しだけ背が低いし、バイコーンに合わせて作られた衣装も、ほんの僅かだけど余裕があるように感じた。
「体の大きさは個人差あるからちょっと私の服だと大きかったかもしれないけど、それでも十分似合ってるよ」
余裕があるといっても、人の指一本入るかどうかだ。まぁ、今人の指じゃないからそもそも入らないんだけど。
「なんか、変な感じがする。声は、変わってないのに、鏡に映る私が、私じゃないから」
「最初はね。慣れるよ徐々に」
バイコーンは私の横に並び立つと、白黒、金銀、対照的な色の馬の幻獣が二人、鏡の向こうに並んでいた。不思議な感じだ。ほんの数時間前まで、学校で授業を受けていた私たちが、今はこうして幻獣として揃って立っているんだから。
「少し歩いたり、屈伸したりして、体の感覚を慣らしていくといいよ」
バイコーンに言われた通り、私は体を少しずつ動かしながら、自分の体の感覚を、自分に馴染ませていく。不思議と、長い角も、大きな体も、すっと自分に馴染んでいく感じがした。最初からそうだったかのように、違和感なく自分の体を動かせるようになるのに時間はかからなかった。
「慣れてきたら、一回戻って、衣装着替えてステージの方に行ってみよっか」
そう言うとバイコーンは、再び体の力を抜く。するとまるで風船がしぼんでいくかのように体が小さくなっていき、それと共にその姿も人間のそれへと、二宮アンの姿へと変わっていった。
私も試しに体の力を抜いて、今内側へと押し込んだ人間の姿の自分を意識して、置き換えてみようとする。すると私の体も小さくなっていき、あっという間に人間の私、一城コウの姿に戻った。
「なんかこれも、変な感じ。この姿で長年生きてきたはずなのに、もう既にちょっと違和感あるもん」
「ね、不思議だよね」
私たちは笑いながら衣装を着替える。今度はステージ用の派手な衣装だ。黒い衣装よりもつくりには大分余裕があって、激しいパフォーマンスが出来るようになっているし、何よりはだけやすくなっている。体が大きくなっても、体を締め付けないように出来ているということだろう。
「よし、じゃあステージの方行こうか」
二宮さんに連れられて、私は舞台の上に立った。昨日は舞台を見下ろしていたのに、今日は客席を見上げる立場になっている。空っぽの客席、そこに人がいて、私のことを見ているとしたら、それはどんな感情だろうか。その時観客が見る私の姿が、ユニコーンの姿だったら、それはどんな感情だろうか。想像するだけで、気持ちがたかぶっていた。
「じゃあ今度は四本の足で立つ自分を想像してみて。これは昨日ステージで一回見てるから、さっきのイメージと合わせれば、きっと一発で出来るんじゃないかな」
「うん、試してみる」
私はドキドキしながら、ステージの真ん中へと歩みを進める。今このステージは貸し切り。観客は勿論、私と二宮さん以外他の店員さんもいない。しんと静まり返ったこの舞台で、私は今から、完全なユニコーンに変身するんだ。
もう一度、自分の姿を意識する。自分の内側のユニコーンを、今度は完全な姿で。足だけじゃない、手も蹄になっている姿を、四つ足でこのステージを跳ね回る姿を、しっかりとイメージするんだ。
……よし、大丈夫。私は一つ息をつき、そして。
「っ!」
また、あの感覚だ。自分の体がはがれる感覚。置き換わる感覚。それと共に、本当に私の体は、一条コウの体は、ユニコーンのそれへと置き換わっていく。
今度は白い毛が生えて、指が太くなるだけじゃない。私の指は完全に一つになって、馬の蹄へと変わっていく。物を持つことも出来ない、走るための蹄だ。体のバランスも大きく変わっていく。二本足で立っているのはつらくなり、私は思い切って前へと体の重心を倒す。完全に蹄に変わった手で――いや、前足で着地をする。その時にはもう、後足も蹄に変化していた。大きくなった体は、さっきまでとは違う、完全な馬の体躯へと変化していた。
「ふぅ……フゥ……ブルル……!」
体だけじゃない。顔もまた、馬のそれへと変化している。純白の毛、黄金のたてがみ。凛々しい鼻先、鋭い角。どこをとっても、人間一城コウの部分は存在しない。今の私は、ユニコーンだ。
完全な、一匹の幻獣だ。
私は、内側から溢れる高揚感から声を上げようとした。けど。
「ヒヒーンッ! ……ブルル……」
私の口から洩れたのは、馬のいななく声だった。見た目だけじゃない。さっきまでは唯一の名残だった声さえも、完全にユニコーンに置き換わってしまったんだ。外側も、内側も、今の私は完全な幻獣なんだ。
「ブルルッ」
その時聞こえてきたのは、私じゃない、別の馬のいななく声だった。声のする方を見ると、そこにいたのは黒い毛並みと銀色のたてがみ、二本の角を持った馬の幻獣だった。
そのいななく声は、ただの幻獣の鳴き声でしかないはずなのに、不思議と誰の声だか分かった。
『どう? 完全な幻獣になった感想は』
黒馬は私のそばへと歩み寄り、ぴたりと肌を寄せてきた。
『うん……すごく、今気持ちがすっきりしてる。自分の中で、すごく、今の姿が、しっくり来てる感じがする』
四本の足をゆっくり動かし、体の感覚を確かめる。今ここにいる自分の、そして横にいるもう一匹の幻獣の、呼吸を、体温を、感じながら。しっかり自分の感覚を、体を馴染ませていく。
『どこかで、この瞬間を、この感覚を、ずっと追い求めていて、でも、自分ではどうしようもなかったから。だから、うん。ここで二宮さんに出会えて、バイコーンに出会えて、そして何より、ユニコーンに、私自身に出会えて、本当に良かった』
『なら、よかった』
黒い馬は、にっこりとほほ笑んだ。それから私達、白と黒の二匹の幻獣はステージの上を、お互いの存在を確かめ合いながら跳ね回った。太陽と月が、互いに昇ったり沈んだりするように。何度も、何度も跳ね回った。
翌日。人間の姿に戻ってまた、普段の日々が始まる。
「コウ、機嫌良いね」
「そう、かな。まぁ、そうかもね」
クラスメイトにそう話しかけられ、私はそんな感じに返事を返す。
「昨日さ、委員長と何かあったでしょ?」
「委員長も、機嫌よかった?」
「よかった」
私は二宮さんの方を見る。明らかに機嫌よさそうだ。いつものよそよそしさは、だいぶ消えていた。
「それって聞いていい話? 聞いちゃダメな話?」
「多分大丈夫だとは思うけど、一応聞いてからね」
私はクラスメイトにそう告げた後、二宮さんに話しかける。
「二宮さん、昨日のことというか、私たちのことってさ、どうする」
「あー……まぁ、そのうち、かな」
「そのうちだって。聞こえてた?」
「聞こえてた。いいよそれでも。心配してないし」
クラスメイトはそう言って笑った。けど。
「ところで、来月またあのカフェ行こうと思うけど、二人はどうする? っていう話は聞いていい?」
あぁ、これはうっすら何かを察されてるなと感じた。
いや、逆か。私たちが、察しているのかもしれない。そもそも、委員長である二宮さんの様子の違いを真っ先に気にしてたのは誰だったか。あのカフェのチラシを持ってきたのは誰だったか。そして一番行きたがってたのは誰だったか。私と二宮さんはお互い察し合ったから気づけたけど、じゃあその時クラスメイトはどこの誰を見ていたのか。私と二宮さん以外にだって、私達みたいな存在は、きっと普通にいるんだ。
「来月と言わずさ、今日でも話聞くよ。天野さん」
「本当? ならこの後ちょっといい? 相談があって――」
そして、それから一カ月後。
結局私たちは――私達二人と、あのクラスメイトは――この日、客としてカフェを訪れることはなかった。
客として、他の仲のいいクラスメイトには声を掛けたし、既にお店に向かってきてるけど、その中に私たちはいない。
「クラスメイトの前でこの姿見せるのって、こんな緊張するんだね。アンちゃん」
私達がいたのは、お店の控室。私は服を着替えた後、おかしなところがないか鏡の前で確認する。
立派な蹄。立派な尻尾。立派なたてがみ。立派な角。
うん、立派なユニコーンだ。衣装もばっちり似合ってる。
「すっかりお似合いですけど、声とキャラクターもしっかり作ってくださいね? ユニコーンさん」
既に支度を終えたバイコーンが、低い声で私にそう話しかけてきた。
「あ、あぁ、んんっあ、あぁ~、ど、どうですかね、こんな感じ?」
低い声の練習もしてはきたけど、これはちょっとまだ慣れてなかった。自分の姿を考えればそっちの方がしっくりくるはずなんだけど、不思議なもので。
「で、そっちはどう? リオちゃん」
私はバイコーンとはまた別の方を向く。そこにいたのは紺色の毛並みを持つ狼頭の青年だった。狼の尻尾、獣の手足とその姿は、服を着て二足歩行している狼そのものだったが、明らかに普通の狼にはない翼が背中から生えていた。
「ぶっちゃけビビってる」
「悪魔族がビビってちゃダメじゃない?」
「だって知ってるでしょ? 私、変身なかなかうまくいかなくて結構ギリだったんだもん」
狼頭の青年は、かわいらしい高い声で弱音を吐いた。
「まぁでもこうなったら、全力でやるしかないでしょ」
「そうそう、私達三人の練習の成果をさ、みんなに見てもらわなきゃ」
私達馬頭二人は、そう言って狼頭を励ました。
「バイコーン、ユニコーン、マルコシアスはそろそろフロア入って!」
その声を聞いた私たち三人は顔を見合わせる。よし、幻獣として異世界人として、そして何よりクラスメイトとして、しっかりみんなも、他のお客さんもおもてなしをしなきゃ!
私達三人は入口に立ち、お客さんを迎え入れる。そして声を揃えて。
「ようこそ異世界カフェへ!」
あなたに、君に、自分に。その言葉がどうか届きますように。
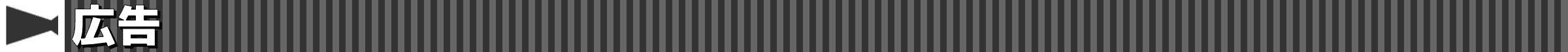
シェア
おすすめ商品(PR)
Amazonのアソシエイトとして、ATRI.PAGEは適格販売により収入を得ています。
この小説を書いた人
タグ
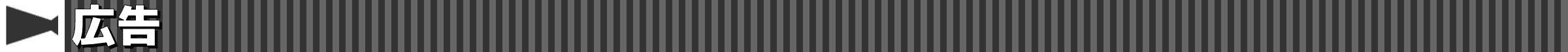
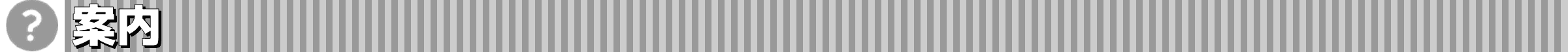
ATRI.PAGEは獣化(TF、transfur)に関する様々なコンテンツを扱うエンタメサイトです。
漫画、小説、記事、特集、エッセイ、作品紹介、動画、生配信など盛り沢山!
毎週土曜日0時ごろ更新!
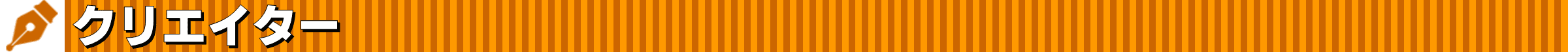


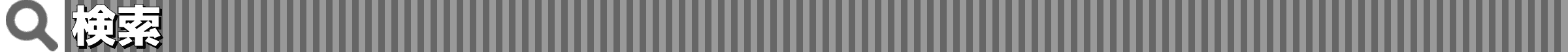
サイト内検索はこちらから!
広告
広告
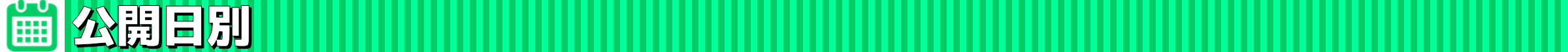
2024/08/31(1)2024/08/17(1)2024/08/10(1)2024/08/03(1)
2024/07/27(1)2024/07/20(1)2024/07/13(1)2024/07/06(1)2024/07/01(1)
2024/06/30(1)2024/06/29(1)2024/06/23(1)2024/06/22(1)2024/06/16(1)2024/06/15(1)2024/06/09(1)2024/06/08(2)2024/06/02(1)2024/06/01(1)
2024/05/26(1)2024/05/25(2)2024/05/19(1)2024/05/18(2)2024/05/12(1)2024/05/11(2)2024/05/04(2)
2024/04/27(2)2024/04/20(2)2024/04/13(2)2024/04/06(3)
2024/03/30(4)2024/03/23(2)2024/03/16(2)2024/03/09(2)2024/03/02(2)
2024/02/25(1)2024/02/24(5)2024/02/17(4)2024/02/10(4)2024/02/03(3)
2024/01/27(4)2024/01/20(3)2024/01/13(3)2024/01/06(4)
2023/12/30(2)2023/12/23(2)2023/12/16(3)2023/12/09(2)2023/12/02(3)
2023/11/25(4)2023/11/18(4)2023/11/13(1)2023/11/11(4)2023/11/07(1)2023/11/06(1)2023/11/04(4)
2023/10/31(1)2023/10/30(1)2023/10/28(4)2023/10/24(1)2023/10/23(1)2023/10/21(4)2023/10/14(4)2023/10/07(4)
2023/09/30(4)2023/09/23(4)2023/09/16(4)2023/09/09(4)2023/09/02(4)
2023/08/26(5)2023/08/19(5)2023/08/12(6)2023/08/05(6)
2023/07/29(7)2023/07/22(6)2023/07/15(6)2023/07/08(5)2023/07/01(13)
広告
広告
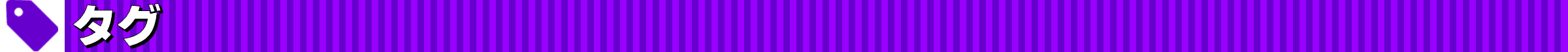
小説
広告
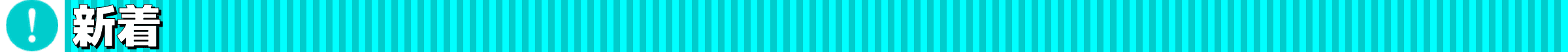
広告
広告